さといも科
テンナンショウ属
テンナンショウ 一名:アオマムシグサ
林の下に自生する多年草、中国・台湾に分布、日本でも希に見られる
土の中に球形の地下茎があり、茎は直立して枝を出さず、高さ40〜60cmとなり柔らかく肉質で、新芽の時は葉柄の変化した皮で包まれ、マムシのような模様がある
葉は2枚で下の葉は小さく、上の葉は大きいが2枚とも同じような複葉である。(5/8自宅にて撮影)
開花は5〜6月

鉢の中で順調に育つ
雄株と雌株は別で、花は筒形のほうで被われ、ほうの先は緑色。
雄花の穂は小さい花がまばらに着き、花粉袋は紫色で、雌花の穂は緑色の子房が沢山着いている。
果実が熟する頃になるとほうが無くなり赤くなって美しい
天南星(テンナンショウ)は中国の言葉で、茎とくに新芽が出たときはマムシのようであり、筒形の包が緑色であるからアオマムシグサという
食すると喉が刺激される有毒植物。
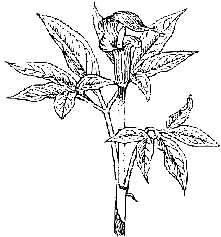
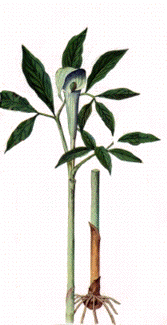
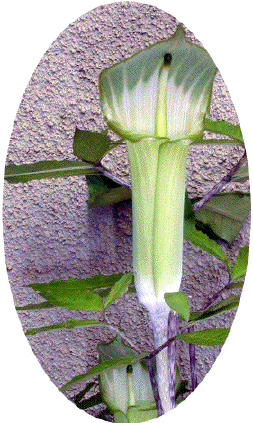
上図;自宅の蜂で開花したテン ナンショウ(5/8撮影)
左図1;テンナンショウの一株
地下茎も確認できる
左図2;テンナンショウの花アップ
長い花柄の先に仏炎包に包まれて花序がつき、花序の先は付属体として長く伸び包から直立。仏炎包の下部は両端が巻き込んでいて筒形。上部は中央付近から前に曲がっている。

テンナンショウ良く成長('08.4.26)

花のみアップ('08.4.26)


































