
2月11日・宮之當「直会」開式
今年の入當者:(左より)岸本良任くん(小学校6年生)、久保和斗くん(小学校3年生)の新入當挨拶

境内の特設座席上で
例年になく暖かく快晴の一日。出席者も多く26名になり、直会も輪・和・話の中で3時間余りが、非常に短く感じ盛会に終わる。
新入當者は世話人の誘導で、最初と最後に党員全員に挨拶をする。

9:30~12:00 参拝、直会(ナオライ)
12:30~13:50 的射の神事、散会
給仕人2人の接待でお互いにお酒を酌み交わし話に花が咲く。
当日は加東市情報センター、加東市教育委員会、東条歴史を掘りおこそう会の皆さんが見学して、ビデオにデジカメ撮影にと賑わった

8升の御神酒も飲み干すには時間は掛からず、後から追加する次第。

直会を祝福しているかのような暖かい一日で、参会者は身体の中も外もポッカポカ。
(後方は観音堂)

包丁株により、直径約25cmの「のし餅」12枚を参会者に配るための「ごくもち」に裁断
半紙に2枚組で包み、世話人が参会者に手渡す
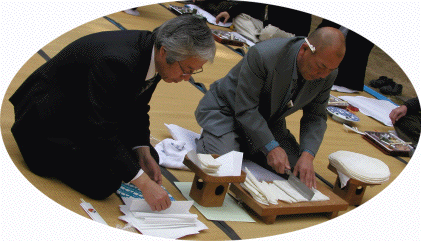
包丁株の「ごくもち」作りと介助役の世話人
周囲からは撮影のシャッター音が境内に響き渡る。
(写真左:世話人、右:久保勝彦氏)

二人の弓株、いざ出陣
弓・矢・的箸を神殿よりおさげして、的射の準備へ(左:岸本昭夫氏、右:長尾農夫也氏)

23メートル後方に設置された直径1m90cmの的

最初の一矢は、弓株の二人が射る
それぞれ的箸2本を的株に挿し、二人が交互に2ほんの矢を射る
新入當者2人は放たれた矢を拾い、次の射者に手渡す

最後に的射の神事を執り行う
1本の的箸を的株に指し、1本の矢を放つ。
的箸24膳(48本)あるから48回弓を引く。
的射の距離は23〜25メートル

的射を待つ者はサイロで暖を取って待つ
(後方の集団が参会者、的前から撮影)

右、神楽殿近くには見学者を見る
弓・矢の位置を賑やかに講釈する参会者もあり、和やかな内に的射の神事が進む。

的射をアップ

参会者が順次的射
後ろの茅葺き建物は「神楽殿」

的射の最後から2番目は末の当人の的射だが、今年は決まっていないため、新當人2人が的射
両者とも小学生のため、父親が手ほどき?射ても、なかなか的までは届かない。
特別参加で新當人も的射を許され弓を引く瞬間

良い想い出の体験ができ、今日という日を忘れずに受け伝えてくれることを切望。

的箸48本の矢も放たれ、片づける弓株
後神殿に報告・納めて閉会となる。
参会者を初め見学者の方々もご苦労様でした!